�k��n�p���㉇���
�k�C����w�n�p���㉇��ɂ���
�k�C����w�n�p���㉇��
�s��@���F
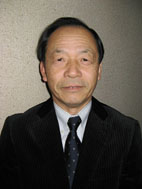
�s�쐐�F�
�u�k�C����w�n�p���㉇��v�́A
�P. �k�C����w�n�p��������
�Q. �㉇��Ɍ��J�����������ʌ㉇���
�ō\������Ă��܂��B�k�C����w�n�p���ւ̌o�ϓI�x���������݂̌𗬂Ȃǂ�ړI�Ƃ��āA���a40�N(1965)�ɐݗ�����܂����B
�����葁���ݗ����ꂽ�u�k��n�p������OB��v�������y�т��̎��ӂɍݏZ�̖k��n�p���ݐЎ҂�����Ƃ��āA���l�̎�|�̊������s���Ă��܂��B�k�C����w�n�p���㉇��Ɩk��n�p�������n�a��́A���̍\������ɂ͏d�����镔��������܂����A�u�k��n�p���̂��߂Ɂv�Ƃ������ʂ̖ړI�̂��߂ɓ�����ٖ��ȏ������ƈӎv�a�ʂ�}��A���͂��Ċ������s���Ă��܂��B
�{��̖ړI�E�Ӌ`�ɂ��Ĉȉ��Ɏ��̍l�����q�ׁA�F����̖{��̊����ւ̈�w�̂����͂����肢�������Ǝv���܂��B
�l���Ă݂܂��ƁA�����̊����́A�ӎ�����Ƃ��Ȃ��ƂɊւ�炸�A�n���ȗ����搶�E��y�ɂ���Ēz���ꂽ���Y�A����͓`���Ƃ����Ă�������������܂��A���̏�ɐ��藧���Ă���킯�ł��B���������̗͂ŏo������̂ł͂Ȃ������͂��ł��B���̎�������Ƃ�邱�Ƃ͂ł��܂��A���������̓_���ɂ��čl���邱�Ƃ͂ł��܂���B�������������łł����ƍl����Ƃ���A����͍��o�ł���A���ʂڂ�ƌ����Ă����������Ȃ��ł��傤�B
���̎��_���炢���Ȃ�A�㉇����͎��炪��������Ɏ��L�`���`�̉��b�����݂̌����ɕԂ��Ă��������ł���Ƃ������Ƃ��ł��܂��B
����A�n���ȗ����X�ƘA�Ȃ�OB�EOG�̘A���́A���݂����N�V���ɂ����Ă���A��X�͂��̒��Ɉʒu�Â����g�ݍ��܂�Ă���킯�ł��B���������_�ł́AOB�EOG�ƂȂ������ł����̐l�������玩����܂��u�㉇�v����Ă���̂��Ƃ������Ƃ��ł��܂����A���ۂɌ𗬂�ʂ��Č㉇����Ă��܂��B ���ԓI�ɂ́A�����̒��j�Ƃ��Ċ����ł���̂́A���������P�N���Q�N�Ԃł�������܂���B�ł����A���̊Ԃ́A���Ԃ�n�Ƃ����������Ƃ̌𗬂�ʂ��ē���ꂽ�S�̋P���́A���̐l�̂��̌�̐l���ɂ����đ��̉����̂ɂ��ς����������̂ɂȂ��Ă��邱�Ƃł��傤�B
�������A�u�l��80�N�v�Ƃ������鍡���ɂ����ẮA������܂��ق�̈�u�ɂ����������AOB�EOG�Ƃ��ĉ߂����l���̕����͂邩�ɒ������Ƃł��傤�B���̂悤�Ȃ��Ƃ��l���܂��ƁA��������OB�EOG�̑S����ɂ킽��𗬁E�e�r�̈Ӗ��Əd�v�������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���݂��Ɋ��m�荇��������Ԃ̌𗬁E�e�r����������ł����A���������ɂƂǂ܂��Ă��Ă͂����Ȃ��ƍl���܂��B
�����̌㉇�����OB�EOG�ɂƂ��āA�ߋ��̃A���o���̂P�y�[�W���߂�����̂����ł͂Ȃ��A�����I�ȈӖ����������Ă��܂��B�n���ȗ����܂��̐l�����̃A���o�C�g�Ŕn�p�����x�����Ă������Ƃ͍ݕ��������Ƃ�����҂Ȃ�N�������g�ɂ��݂Ēm���Ă��܂��B����䂦�N�����n�p���ɁA�����ɁA�������ɗ����Ƃ��������A�ƍl���Ă��������Ă��܂��B
�n�p�͗B�ꓮ���ƂƂ��ɍs���X�|�[�c�ł��B�j�����̂Ȃ��B��̃X�|�[�c�ł��B���̖��͂ɐG�ꂽ��т�ƂɁA���܂͂��̌��t�Ō����A������OB�EOG���g�E�B���E�B���h�̊W��z���A�e�l�̐l��������w�[�������K�����ɖ��������̂ɂ��邱�ƂɌ㉇�������^�ł�������ȂƎv���܂��B�F����̖{��̊����ւ̈�w�̎Q���Ƃ����͂����肢�������܂��B
��� �k��n�p���u�����v�E�㉇��u��v
| �����O | �A�C�N�� | ���@�l | |
|---|---|---|---|
| ���@�� | �i��@��v | ���a�@�T�N�R���` | *S52.3.11�v(90��) |
| ���� | �����@���M | ���a�@�U�N�P���` | *S49.3.25�v(89��) |
| ��O�� | ���V�@���� | ���a�@�X�N�T���` | *S48.12.1�v(82��) |
| ��l�� | ���`�@�N�� | ���a�P�S�N�S���` | *S53.5.31�v(79��) |
| ��ܑ� | ���{�@�v�� | ���a�R�V�N�S���` | *S39.2.13�v(56��) |
| ��Z�� | ���V�@���Y | ���a�R�V�N�V���` | *H18.5.4�v(96��) |
| �掵�� | �͓c�[��Y | ���a�S�W�N�S���` | *H29.3.16�v(89��) |
| �攪�� | ���r�@��j | ���a�T�Q�N�S���` | *H18.7.2�v(81��) |
| ���� | �V���@�P�� | ���a�U�R�N�S���` | *H22.9.20�v(79��) |
| ��\�� | �s��@���F | �����@�U�N�S���` | |
| ��\��� | ���@�� | �����P�U�N�S���` |
| ���i�n���j�F | �@�k�C���鍑��w��n�� | �吳14�N 1�� |
| �A�k�C���鍑��w������n�p�� | ���a 5�N3�� | |
| �B�k�C���鍑��w�\�ȟN����n�p�� | ���a15�N 1�� | |
| �C�k�C����w�̈��n�p�� | ���a26�N 9�� | |
| �D�k���n���D�� | ���a29�N�ݗ� |
| �����O | �A�C�N�� | ���@�l | |
|---|---|---|---|
| ���@�� | ���V�@���� | ���a�R�X�N�P�Q���` | *S48.12.13�v(82��) |
| ���� | ���`�@�N�� | ���a�S�T�N�@�U���` | *S53. 5.31�v(79��) |
| ��O�� | ���V�@���Y | ���a�S�W�N�@�S���` | *H18.5.4�v(96��) |
| ��l�� | �V���@�P�� | �����@�U�N�@�S���` | *H22.9.20�v(79��) |
| ��ܑ� | �s��@���F | �����P�V�N�@�T���` |
�㉇��ݒn
��001-0023�@�D�y�s�k��k23��12����
�㉇������@
| ��@�� | �s��@���F | �iS38�j |
| ��� | ����@���� | �iS34�j |
| ������ | �t�c�@���F | (S44) |
| �ꖱ���� | ���c�@��l | (S59) |
| ���@�� | �����@���� | (S42) |
| �{���@�m�� | (S51) | |
| �{��@�h�� | (S53) | |
| �R�{�@�T�� | (S53) | |
| ���z�@���� | (S59) | |
| ���@�N�� | (S60) | |
| �����@��j | (S63) | |
| �ΐ�@�M�s | (H2) | |
| �����@�W�j | (H9) | |
| ���@�m�j | (H12) | |
| �x���@���Y | (H15) | |
| �ā@�� | ���V�@���Y | (S41) |
| ��c�@���q | (H6) | |
| �k�C������ | �����@�� | (H16) |
| �R��@�ϖ� | (H21) | |
| �]���@�ɑ� | (H24) | |
| �������� | �c���@��j | (H11) |
| ����@�N�_ | (H12) | |
| �|�{�@�a�� | (H13) | |
| �X�c�@���V | (H14) | |
| ����@���� | (H14) | |
| ���R�@����( | (H14) | |
| ��F�@�^�� | (H19) | |
| ���c�@���m | (H25) |
�㉇��K��@
�k�C����w�n�p���㉇��K��
�i2019�N6�������j
| ��1�� | ���� | ||||
| �k���́l | |||||
| ��1�� | �{��́A�k�C����w�n�p��(�k��n�p��)�㉇��Ə̂���B | ||||
| �k�������l | |||||
| ��2�� | �{��́A�傽�鎖�������D�y�s�k��k23��12���ږk��n�p�����ɒu���B | ||||
| ��2�� | �ړI�y�ю��� | ||||
| �k�ړI�l | |||||
| ��3�� | �{��́A�k��n�p���̊����ɑ��Ďx�����s���ƂƂ��ɁA������݂̐e�r��}�邱�Ƃɂ��A�n���v�z���y�ɍv�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B | ||||
| �k���Ɓl | |||||
| ��4�� | �{��́A���̖ړI��B�����邽�߁A���̎��Ƃ��s���B | ||||
�i1�j |
�k��n�p���̊����̎x���ɌW�鎖�� | ||||
| �@ | �k��n�p���̉^�c�ɌW��x�� | ||||
| �A | �k��n�p���ւ̌o�ϓI�x�� | ||||
�i2�j |
������݂̐e�r�ɌW�鎖�� | ||||
| �@ | ����e�r��̊J�� | ||||
| �A | �k��n�p�����Ƃ̌𗬐e�r��̊J�� | ||||
�i3�j |
���̑��́A�{��̖ړI��B�����邽�߂ɕK�v�Ȏ��� | ||||
| ��3�� | ����y�щ�� | ||||
| �k����y�ю^������l | |||||
| ��5�� | �{��̉���́A�k��n�p���̑����ҁA�y�сA�ݕ��o����(���ʉ��)�Ƃ���B | ||||
| 2. | �{��̎^������́A�� 3 ���̖{��̖ړI�Ɏ^������l���͒c�̂ł����āA�������������F�����҂Ƃ���B | ||||
| �k���l | |||||
| ��6�� | �{��̉���y�ю^������́A������ɂ����ĕʂɒ�߂����[��������̂Ƃ���B | ||||
| ��4�� | ���Y�y�щ�v | ||||
| �k���Y�̊Ǘ��l | |||||
| ��7�� | �{��̍��Y�͗��������Ǘ����A���̕��@�͗�����̋c�����o�āA���������ʂɒ�߂�B | ||||
| �k���Y�̍\���l | |||||
| ��8�� | �{��̍��Y�́A���Ɍf������̂������č\������B | ||||
| �i1�j | ������ | ||||
| �i2�j | ��t���i | ||||
| �i3�j | ���Y���琶������� | ||||
| �i4�j | ���Ƃɔ������� | ||||
| �i5�j | ���̑��̎��� | ||||
| �k���ƔN�x�l | |||||
| ��9�� | �{��̎��ƔN�x�́A���N1��1���Ɏn�܂�12��31���ɏI���B | ||||
| �k���ƌv��y�ї\�Z�l | |||||
| ��10�� | �{��̎��ƌv��y�т���ɔ������x�\�Z�́A���������쐬���A������̋c�����o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B | ||||
| �k���ƕy�ь��Z�l | |||||
| ��11�� | �{��̎��ƕ��A���x�v�Z���A�ݎؑΏƕ\�y�э��Y�ژ^���̌��Z�Ɋւ��鏑�ނ́A�����ƔN�x�I����A���₩�ɁA���������쐬���A�Ď��̊č����A������̋c�����o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B | ||||
| ��5�� | ���� | ||||
| �k�����l | |||||
| ��12�� | �{��ɁA���̖�����u���B | ||||
| �i1�j | ���� 10���ȏ� | ||||
| �i2�j | �Ď� 2���ȏ� | ||||
| �i3�j | ���� 8���ȏ� | ||||
| 2. | �����̂���1������A1����A1���𗝎����A2����ꖱ�����Ƃ���B | ||||
| �k�����̑I�C�l | |||||
| ��13�� | �����A�Ď��y�ъ����͎��E�A���E�ɂ����҂��藝����ŋ��c�����肷��B | ||||
| 2. | ��A����A�������y�ѐꖱ�����́A������̌��c�ɂ�藝���̒�����I�C����B | ||||
| �k�����̔C���l | |||||
| ��14�� | �����̔C����2�N�Ƃ��A�ĔC�͂����W���Ȃ��B | ||||
| 2. | �Ď��̔C���� 4 �N�Ƃ��A�ĔC�͂����W���Ȃ��B | ||||
| 3. | �����̔C���́A���ɂ�����߂Ȃ��B | ||||
| �k�����̐E���l | |||||
| ��15�� | �����́A��������\�����A������̋c���Ɋ�Â��A�{��̋Ɩ������s����B | ||||
| 2. | ��́A�{����\����B | ||||
| 3. | ����́A���⍲���A��Ɏ��̂���Ƃ��́A���̐E�����s����B | ||||
| 4. | �������́A�{��̋Ɩ�������B | ||||
| 5. | �ꖱ�����́A��������⍲���A �������Ɏ��̂���Ƃ��́A���̐E�����s����B | ||||
| 6. | �Ď��́A���Ɍf����Ɩ����s���B | ||||
| (1) | ��̋Ɩ����s�y�щ�v�̏��č����A���ƔN�x�I�����ɗ�����ŕ���B | ||||
| (2) | �O���ɂ����ĕs���Ȏ����������Ƃ��͕K�v�ɉ����ė���������W���A����B | ||||
| 7. | �����́A�㉇����ɕK�v�Ȏ�����Ƃ��s���B | ||||
| ��6�� | ������ | ||||
| �k��ށl | |||||
| ��16�� | ������́A�ʏ헝����ƗՎ��������2��Ƃ���B | ||||
| �k�\���l | |||||
| ��17�� | ������́A�����������č\������B | ||||
| �k���\�l | |||||
| ��18�� | ������́A���̎��������c����B | ||||
| �i1�j | �{�K��̕ύX�A���p | ||||
| �i2�j | �{��̖ړI�Ɏ^������l���͒c�̂̓��� | ||||
| �i3�j | ���ƌv��y�ю��x�\�Z���тɂ��̕ύX | ||||
| �i4�j | ���ƕy�ю��x���Z | ||||
| �i5�j | �����̌ݑI | ||||
| �i6�j | �{��̉���̉�� | ||||
| �i7�j | �{��̎��ƂɌW��K���̐���y�сA�ύX�A���p | ||||
| �i8�j | ���̑��A�{��̉^�c�Ɋւ���d�v���� | ||||
| �k�J�Ál | |||||
| ��19�� | �ʏ헝����́A���N1��ȏ�J�Â���B | ||||
| 2. | .�Վ�������́A���̊e���̈�ɊY������ꍇ�ɊJ�Â���B | ||||
| (1) | ���������K�v�ƔF�߂��Ƃ��B | ||||
| (2) | ����������3����1�ȏォ���c�̖ړI�ł��鎖�����L�ڂ������ʂ������ď��W�̐��� ���������Ƃ��B | ||||
| (3) | �Ď����珵�W�̐������������Ƃ��B | ||||
| 3. | ������́A������2����1�ȏ�̏o�Ȃ��Ȃ���ΊJ�Â��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B | ||||
| �k���W�l | |||||
| ��20�� | ������́A�����������W����B | ||||
| 2. | �������́A�O���2���̑�2���y�ё�3���̋K��ɂ�鐿�����������Ƃ��́A���̓�����15���ȓ��ɗ���������W���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B | ||||
| �k�c���l | |||||
| ��21�� | ������̋c���́A����������ɓ�����B | ||||
| �k���c�l | |||||
| ��22�� | ������̌��c�́A�o�ȗ����̉ߔ����������čs���B | ||||
| 2. | ��ނȂ����R�ɂ��o�Ȃł��Ȃ��������A���炩���ߒʒm���ꂽ�����ɂ��ď��ʂ��邢�͓d���I�L�^�ɂ��ӎu�\���������Ƃ��́A���c�ɉ�������Ƃ݂Ȃ����ƂƂ���B | ||||
| �k�c���^�l | |||||
| ��23�� | ������̋c���ɂ��ẮA���Ɍf���鎖�����L�ڂ����c���^���쐬���A�����ۑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B | ||||
| (1) | �����y�яꏊ | ||||
| (2) | �����̌��ݐ��y�яo�Ȃ��������̎���(���ʖ��͓d���I�L�^�ɂ��\���҂ɂ��ẮA���̎|�L���邱��)�B | ||||
| (3) | �R�c�����y�ыc������ | ||||
| (4) | �c���̌o�߂̊T�v�y�т��̌��� | ||||
| (5) | �c���^�����l�̑I�C�Ɋւ��鎖�� | ||||
| 2. | �c���^�ɂ́A�c���^�����l2���ȏオ�A�c���ƂƂ��ɋL�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B | ||||
| ��7�� | ���_��y�ьږ� | ||||
| ��24�� | �{��ɖ��_���u�����Ƃ��ł���B | ||||
| 2. | ���_��́A��������肵�A��������������Ϗ�����B | ||||
| ��25�� | �{��Ɍږ��u�����Ƃ��ł���B | ||||
| 2. | �ږ�́A��������肵�A��������������Ϗ�����B | ||||
| ��8�� | �⑥ | ||||
| �k�K���l | |||||
| ��26�� | �{��̎��Ɛ��s��ŕK�v�ȋK���́A������̌��c�ɂ�萧�肷��B | ||||
| �t�� | |||||
| ���̋K��́A2019�N6�����{�s����B | |||||
�k��n�p������OB���
����OB��ɂ���
����OB��_�
�������

����������_�
�k��n�p������OB��́A���a34�N�ɒa�����܂����B����܂ł͑S���I�Ȍ㉇��g�D���A�ł��Ă��Ȃ����̂��Ƃł��B�����ɂƂ���OB�̑g�D���͔O��̂��Ƃł������A�܂������ɂ͎����Ă��܂���ł����B
���a34�N�A��OB�̗L�u���W�܂茟�����d�˂����ʁA�܂�����OB���ݗ����Ĕn�p���ւ̎x�����n�߂邱�Ƃɂ����̂ł��B
���a34�N11���A�S���{�̋��Z��ɏo�ꂷ��n�p���̊��}������˂āA�u����OB��v�̑n������J�Â���܂����B�n�p���ւ̎x���E������݂̐e�r�𒌂Ƃ��銈�����j����܂�A�������i��9���j�E������������i��34���j�����߂āA����OB��������܂����B
�n�p�����A�n���������̋��Z��ɎQ������Ƃ��̊��}��́A���̌�A���N�ɂ킽���Č�����OB�̌𗬂̏�ɂȂ��Ă��܂��B����̐e�r�ɂ��ẮA��n��E�ύ���Ƒ����܂߂Ă̏W�܂�Ȃǂ��Â���Ă��܂����B
����OB��̔����I�ɂ���Ԍo�߂̒��ł́A�ꎞ���̊��������������������܂������A�V���Ȏ��g�݂��n�܂��Ă��܂��B�k��{���ւ́u�|�v�����؍Đ����Ɓv�̋��͂��s���Ă��܂����B���݁A���ƂȂ��Ă���s���ɂ́A1���̑���E�V�N��A11���̑S���{�̋��Z��ɎQ�����錻���̊��}�����܂��B
�k��n�p���Ƃ������ʂ��J�Ō���Ă���OB�́A���ꂩ����������x������͂ɂȂ肽���Ǝv���Ă��܂��B�����EOB�̊F����A�k��n�p�����x�����Ă���������X�A�@��������A�u����OB��v�̏W�܂�ɂ��ł��Q�����Ă��������B���}�������܂��B
